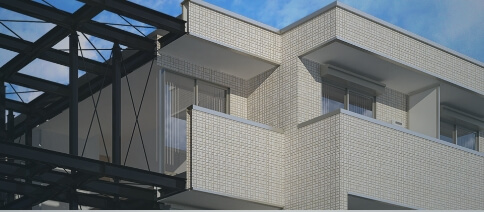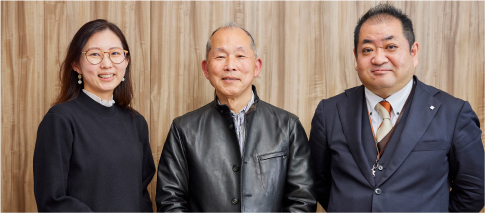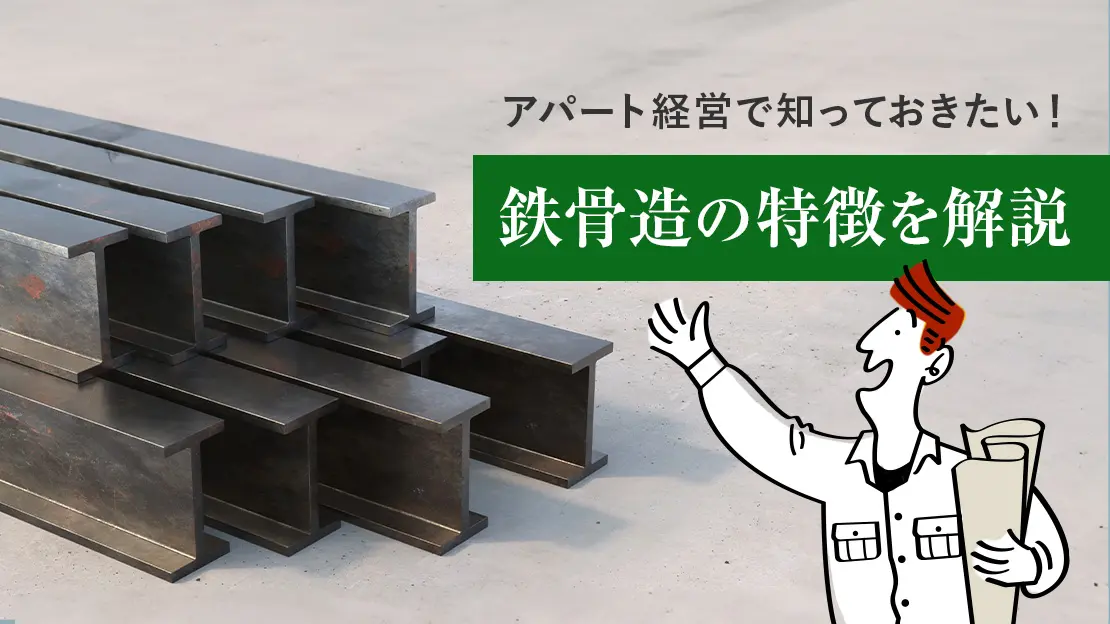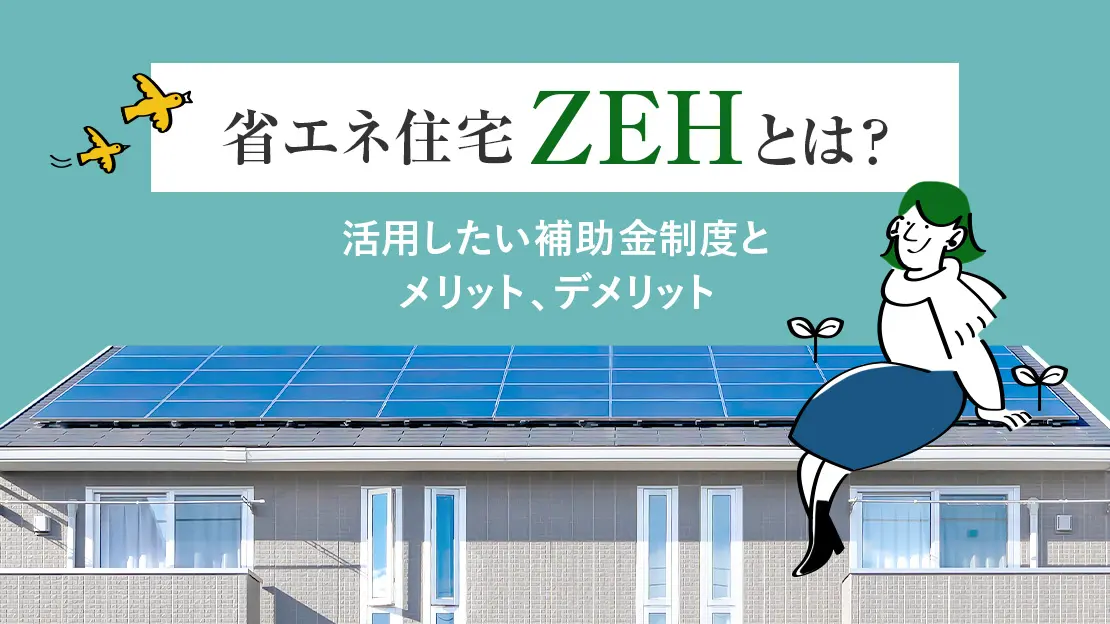アパート経営を始める際、気になるのが「初期費用はどのくらい必要なのか」という点ではないでしょうか。アパートを新築または購入するには多額の資金が必要になり、資金計画をしっかり立てることが成功のカギとなります。アパート経営の初期費用には、アパートを取得するための「建築費」と、ローン手数料や税金などの「諸費用」があり、それぞれの内訳を正しく理解することが大切です。さらに、アパート経営を継続するためには維持費用もかかるため、事前に収支計画を立てることで安定した経営が可能になります。
この記事では、アパート経営の初期費用の種類や維持費用の種類、自己資金の目安について解説します。アパート経営を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
アパート経営のメリットや流れなどの基礎知識についてはこちらの記事をご覧ください
いまさら聞けない!
アパート経営の疑問を解消
自己資金、利益、空室対策…
アパート経営によくある不安と解決策をまとめました。
今なら無料で、メールにてお届けします。

アパート経営に必要な初期費用には建築費と諸費用の2つがある

アパート経営における初期費用とは、物件の取得費用だけでなく、家賃収入を得るまでに必要なすべての経費を含みます。大きく2つに分けると、まず建築費があります。建築費は、実際にアパートを新築または購入する際に必要な費用です。また、建築費はアパートの本体工事費と、上下水道や外構などの別途工事費に分けられ、物件の規模、立地、工事内容によって大きく変動します。
もう1つの費用として諸費用があります。諸費用は、ローン手数料、登記費用、不動産取得税、印紙税、火災保険や地震保険など各種保険料が含まれたものです。
また、アパート経営では初期費用だけでなく、定期的に発生する維持費用も物件の収益性に大きく影響します。初期費用を抑えながら、維持費用を適切に管理することが、長期的に利益を上げるためのポイントです。
アパート経営の初期費用の種類
アパート経営の初期費用は、前述のとおり大きく分けて建築費と諸費用の2種類に分けられます。それぞれの費用の具体的な内訳について見ていきましょう。
建築費
建築費は、アパート経営における初期費用の中で、最も大きな割合を占める費用です。
建築費には、アパート本体を建設するための「本体工事費」と、給排水設備や外構工事などにかかる「別途工事費」が含まれます。本体工事費と別途工事費の詳細は下記のとおりです。
本体工事費
本体工事費は、アパート本体を建築するための費用です。
一般的に、アパートの規模が大きくなったり、建物の形状が複雑になったりするほど、本体工事費も高くなる傾向があります。
さらに、アパートを建築する土地の条件も本体工事費に影響を与えるため注意が必要です。狭い道路に面している土地や住宅が密集しているエリアでは、大型の工事用トラック・重機を使用できない場合があり、その結果、作業効率が低下して本体工事費が割高になる可能性があります。
本体工事費は、アパート経営の初期投資の大部分を占めるため、コストを抑えつつも、長期的な収益性を考慮した建築計画を立てることが重要です。
別途工事費
別途工事費は、本体工事費に含まれない付帯工事の費用です。
地盤改良や給排水工事、電気・ガス設備の工事、外構工事などが該当します。付帯工事はアパート経営に欠かせないものですが、土地の条件や周辺環境によって費用が大きく異なるため注意しましょう。例えば、地盤が軟弱な土地では、アパートを安全に建てるために地盤改良工事が必要となり、追加費用が発生します。また、周囲に既存の建物が少ない地域では、水道管やガス管を本管から引き込む距離が長くなるため、その分工事費が高くなる傾向があります。
別途工事費は、本体工事費と比べると見落とされがちですが、予想外の追加費用が発生する場合もあるため、事前に工事内容を把握し、必要な費用を見積もっておくことが大切です。
諸費用
諸費用は、ローン手数料や登記費用、不動産取得税、印紙税、火災保険料などの費用です。
一般的に、諸費用はローンではまかなえないため、自己資金として準備する必要があります。諸費用は、物件の規模や融資の条件によって異なりますが、初期費用全体の10%~20%程度を占めることが多いでしょう。諸費用を事前に把握し、資金計画に組み込んでおくことで、スムーズにアパート経営をスタートできます。諸費用の具体的な内訳については下記のとおりです。
ローン手数料
ローン手数料は、融資を申し込む際に金融機関へ支払う事務手数料のことで、借入額や金融機関の条件によって異なります。
ローンを利用する際には、金融機関が融資のリスクをカバーするために保証会社を利用することがあり、その際に保証料が発生する場合があります。保証料は借入額や返済期間によって異なりますが、一括前払い方式と分割支払い方式のいずれかを選択できることが一般的です。
アパートローンの基礎知識についてはこちらの記事をご覧ください
登記費用
登記費用は、アパートを新築または購入した際に、不動産の所有権を正式に登録するための登記手続きの費用です。
登記にはいくつかの種類があり、それぞれに費用が発生します。まず、「保存登記費用」は、新築したアパートの所有権を登録する際にかかる費用です。次に、ローンを利用して物件を新築または購入する場合は、金融機関が担保として設定する「抵当権設定登記費用」も発生します。また、新築の場合には、建物の物理的な状態を明確にするための「表示登記費用」も必要です。
なお、登記費用の内訳として、「登録免許税」と「司法書士報酬」があります。登録免許税は、登記の種類や物件の評価額に応じて決まる税金で、国税庁「登録免許税の税額表」によると、通常は固定資産税評価額の0.15%(軽減措置適用時)~2.0%程度がかかります。一方、司法書士報酬は、登記手続きを依頼する場合に発生する費用で、依頼する司法書士によって異なりますが、一般的には数万円~十数万円程度です。
不動産取得税
不動産取得税は、アパートを新築または購入した際にかかる税金です。
固定資産税のように毎年支払うものではありませんが、取得後約6ヵ月~1年半後に請求されるため、事前に支払いのタイミングを把握しておきましょう。
総務省「不動産取得税」に記載があるとおり、不動産取得税は「固定資産税評価額×3%(税率)」で求められます。固定資産税評価額とは、自治体が定める不動産の公的な価格で、一般的に市場価格(時価)よりも低めに設定されているのが特徴です。なお、2027年3月31日までは軽減措置が適用され、税率は本来の4%から3%に引き下げられています。
また、新築住宅の場合、「特例」によって税額が軽減されるケースがあります。例えば、一定の条件を満たす住宅用の土地では、不動産取得税の軽減措置を受けられる可能性があるため、事前に自治体の税務課などで確認することをおすすめします。
印紙税
印紙税は、不動産の売買契約書や建築工事請負契約書を作成する際に必要な税金です。
契約金額に応じて税額が決まり、契約書に印紙を貼付することで納税します。
■契約金額別の印紙税額
| 契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 500万円超~1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 60,000円 |
出典:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
また、一定の条件を満たす場合、軽減措置が適用されることもあります。例えば、電子契約を利用することで印紙税が不要になるケースもあるため、契約方法について事前に確認しましょう。
各種保険料
アパート経営では、火災や地震、入居者トラブルなどのリスクに備えるために、適切な保険に加入することが大切です。
特に、金融機関のローンを利用する場合、火災保険への加入が義務付けられるケースが多く、保険料も初期費用の一部として考えておく必要があります。
火災保険は、建物が火災や落雷、台風などの災害で損害を受けた場合に補償を受けられる保険です。補償範囲や契約内容によって保険料は異なりますが、アパートの構造、規模、立地条件によっても金額が変動します。
地震保険は、火災保険に付帯する形で加入し、地震による建物の損害を補償するものです。保険料は、建物の所在地や構造によって決まり、耐震性能が高い建物ほど保険料が安くなる傾向があります。
アパート経営の維持費用の種類

アパート経営では、初期費用だけでなく継続的に発生する維持費用も考慮する必要があります。主な維持費用は、「維持・管理費」「税金」「修繕費」「ローン返済費」です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
維持・管理費
維持・管理費は、アパート経営をしていくために定期的にかかる費用です。
アパートの維持・管理には、共用部分の清掃や設備の点検、家賃の回収、入居者からの問い合わせ対応、退去時の原状回復など、多岐にわたる業務が含まれます。これらの管理をスムーズに行うことで、入居者の満足度を向上させ、空室リスクを抑えることができるでしょう。
維持・管理費には、オーナー自身が対応する場合の実費負担のほか、管理会社に委託する場合の管理委託費があります。管理会社に依頼すると、業務の負担を軽減できるメリットがありますが、管理委託手数料が発生します。
また、定期的な設備点検や修繕も維持・管理費の一部として考えておくことが必要です。例えば、エレベーターや給排水設備の点検、防犯カメラのメンテナンスなど、建物の安全性・快適性を維持するためのコストがかかります。
賃貸住宅の管理を委託するメリット・デメリットについてはこちらの記事をご覧ください
税金
アパート経営では、毎年さまざまな税金が発生します。
主な税金には、「所得税・住民税」「固定資産税・都市計画税」があり、それぞれの仕組みを理解し、適切な対策を講じることが大切です。
まず、アパート経営による家賃収入は、不動産所得として課税対象になります。所得税や住民税は、家賃収入から必要経費を差し引いた所得に対して課税されるため、適切な経費計上を行うことで税負担を軽減できます。
固定資産税・都市計画税は、アパートを所有している限り毎年支払う必要がある税金です。固定資産税は不動産の固定資産税評価額にもとづいて計算され、税率は1.4%が標準とされています(自治体によって異なる場合あり)。都市計画税は、市街化区域内にある不動産に適用される税金で、税率は最大0.3%です。
アパート経営でかかる固定資産税についてはこちらの記事をご覧ください
これらの税金は、地域や物件の種類によって軽減措置が適用されることがあります。例えば、地方税法第349条の3の2「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」を活用することで、小規模住宅用地(200平方メートル以下)の固定資産税を6分の1に減額できるケースがあります。
土地の固定資産税評価額の決まり方についてはこちらの記事をご覧ください
修繕費
修繕費は、アパートや周辺設備が老朽化・破損した場合の修理代金です。
アパート経営を長期間続けるためには、定期的な修繕が欠かせません。建物や設備は年数が経過するにつれて老朽化するため、適切なメンテナンスを行わないと、入居者の満足度が低下し、空室リスクが高まる可能性があるでしょう。
修繕費には、大きく分けて「日常的な修繕」と「大規模な修繕」の2種類に分けられます。日常的な修繕には、給排水設備の故障修理や外壁のひび割れ補修、エアコン・給湯器の交換などが含まれます。一方、大規模な修繕は、築15年~20年を目安に行われることが多く、外壁塗装の塗り替えや屋根の補修、防水工事など、高額な費用がかかるのが特徴です。
なお、修繕費は予期せぬタイミングで発生することもあるため、毎月の家賃収入の一部を修繕積立金として確保することをおすすめします。特に、築年数が古くなるにつれて修繕費の負担が増えるため、長期的な視点で資金計画を立てることが求められます。
ローン返済費
ローン返済費は、アパート経営を始める際に金融機関からの融資を利用した場合に必要な費用です。
ローンを活用することで、自己資金の負担を抑えながらアパートを新築または購入できますが、その分、毎月のローン返済が発生します。
ローン返済費は、借入金額・金利・返済期間によって決まり、毎月の家賃収入から支払うことが一般的です。ローン返済額が家賃収入の50%以下に収まるように計画を立てると、収益の安定性を保ちやすくなるでしょう。
また、ローンの金利タイプには「固定金利」と「変動金利」があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。固定金利は返済額が一定のため、長期的な資金計画を立てやすいですが、その多くは変動金利よりも金利が高めに設定されます。一方、変動金利は金利が低く設定されることが多いですが、市場の金利変動によって返済額が増加するリスクがあるため注意が必要です。
いまさら聞けない!
アパート経営の疑問を解消
自己資金、利益、空室対策…
アパート経営によくある不安と解決策をまとめました。
今なら無料で、メールにてお届けします。

アパート経営に必要な自己資金の目安
アパート経営を始める際に必要な自己資金の目安は、一般的に「初期費用全体の1割~3割程度」とされています。ローンを活用する場合でも、全額を借り入れられるわけではなく、一定の自己資金を準備する必要があります。
特に、金融機関の融資条件によっては、建築費の7割程度までしか借り入れできないこともあり、その場合は建築費総額の3割以上の自己資金が必要です。また、諸費用(ローン手数料・登記費用・税金・保険料など)は、基本的にローンではまかなえないため、自己資金として準備しなければなりません。
なお、自己資金を多く用意できるほど、借入額を抑えられ、毎月のローン返済負担が軽減できます。無理のない資金計画を立てるためにも、自己資金の割合や活用方法を慎重に検討し、長期的なアパート経営の安定性を確保しましょう。
アパート経営の初期費用と維持費を把握し、計画的に準備しよう
アパート経営を始めるためには、初期費用や維持費用、自己資金の目安を正しく理解し、適切な資金計画を立てることが不可欠です。建築費や諸費用だけでなく、アパート経営を続ける上で発生する維持費用もしっかりと考慮し、長期的に安定した収益を確保できるようにしましょう。
また、アパート経営を検討する際には、信頼できる不動産会社や管理会社のサポートを受けることも重要です。資金計画やローンの選び方、運営のアドバイスを受けながら進めることで、リスクを抑えながらアパート経営ができます。
セレ コーポレーションでは、アパート経営のサポートを総合的に提供しています。初期費用や資金計画について不安がある方は、ぜひセレ コーポレーションのサービスをチェックしてみてください。
いまさら聞けない!
アパート経営の疑問を解消
自己資金、利益、空室対策…
アパート経営によくある不安と解決策をまとめました。
今なら無料で、メールにてお届けします。

< この記事の監修者 >

斎藤 岳志
FPオフィス ケセラセラ横浜代表
1977年横浜市生まれ。2001年上智大学文学部哲学科卒。
百貨店、税理士事務所、経営コンサルタント会社勤務などを経て、2013年にケセラセラ横浜を開設。
信用取引や商品先物取引、FXなど様々な投資を経験し、その中で自身に一番合うと感じた大家業を2007年にスタート。不動産投資に関するアドバイスを中心としたファイナンシャルプランナーとして活動中。
金融資産は、イデコやNISAを活用しながら、実物資産は、中古ワンルームを活用しながら、
身銭を切って、自らも資産形成中のプレイヤーでもある。