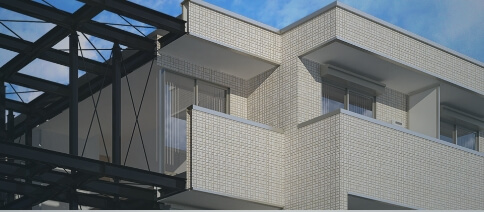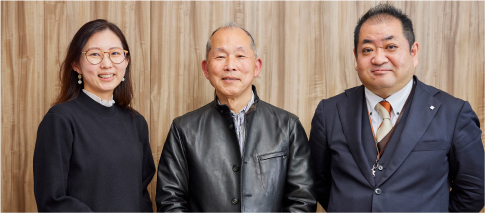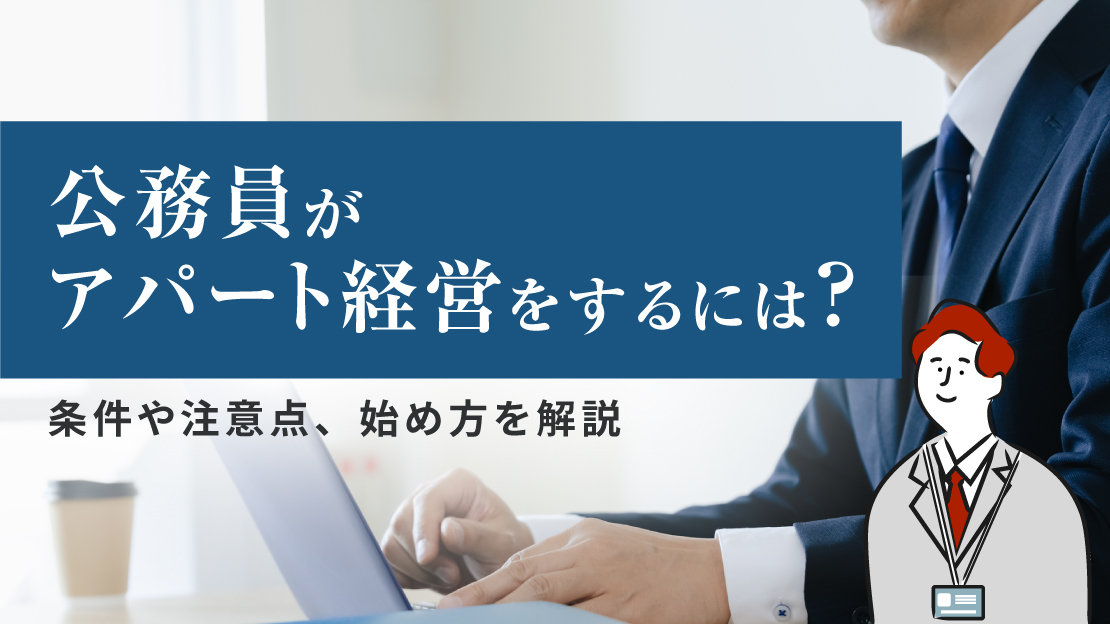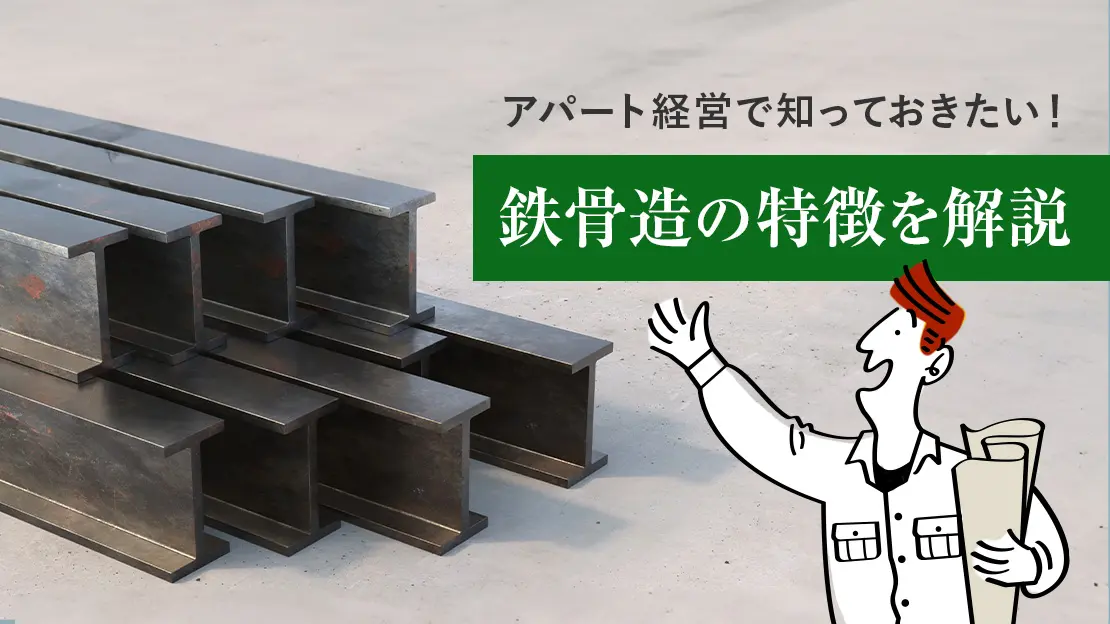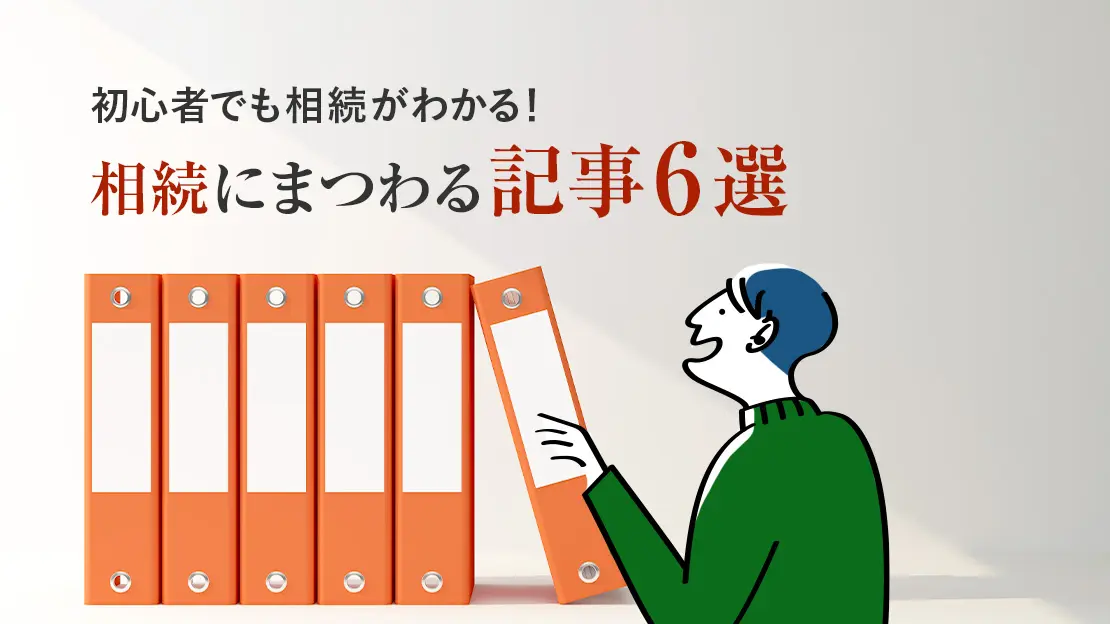副業が原則禁止されている公務員でも、一定の条件を満たせば合法的にアパート経営を行うことができます。安定した収入を活かして将来の資産形成を考える公務員の方にとって、アパート経営は魅力的な選択肢です。しかし、どのような条件なら許可が不要なのか、申請が必要な場合はどう対応すべきか、わからない点も多いのではないでしょうか。
この記事では、公務員がアパート経営を行うための具体的な条件や申請が必要な場合の手続きのほか、アパート経営を始めるステップなどについて詳しく解説します。
いまさら聞けない!
アパート経営の疑問を解消
自己資金、利益、空室対策…
アパート経営によくある不安と解決策をまとめました。
今なら無料で、メールにてお届けします。

公務員でもアパート経営はできる?
結論からいえば、公務員でもアパート経営は可能です。公務員は国家公務員法や地方公務員法により、副業が原則として禁止されています。これらの法律の中で、信用失墜行為の禁止や秘密保持義務、職務専念義務、私企業からの隔離など、副業に関しての制限があるためです。
しかし、一定規模以下のアパート経営については資産運用とみなされ、副業には該当しないため、許可なく行うことができます。条件を守ることで、公務員としての職務に支障をきたさず、法的にも問題なくアパート経営を行えるのです。
ただし、条件を超えた規模や収入の場合は、所属機関に自営兼業承認申請書を提出し、許可を得る必要があります。まずは自分の状況が条件に該当するかを確認し、必要に応じて適切な手続きを踏むことが重要です。
公務員が許可不要でアパート経営ができる条件
では、公務員が許可を得ずにアパート経営を行うには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。ここでは、公務員が許可不要でアパート経営を行える条件について解説します。
5棟10室未満の物件規模に抑える
公務員が許可不要でアパート経営を行うには、物件規模を5棟10室未満に抑えることが基本的な条件です。具体的には、独立家屋なら5棟未満、アパートやマンションなら10室未満であれば、許可なく経営を行える場合が多いといえます。この規模を超えると副業と見なされる可能性が高まるため、注意が必要です。
ただし、この条件はあくまで1つの目安であり、自治体や所属機関によって判断基準が異なることもあります。そのため、アパート経営を始める前に、自分の所属する人事部や管理部門で具体的な基準を確認しておくことが大切です。
年間家賃収入を500万円未満にする
公務員が許可不要でアパート経営ができる条件としては、年間家賃収入を500万円未満にすることも挙げられます。物件規模だけでなく、収益の規模も副業に該当するかどうかの判断材料となり、年間家賃収入が500万円未満であれば、営利性が低いと判断され、副業とは見なされにくくなります。
戸建賃貸や駐車場経営についても同様に、件数や台数の制限があるため、複合的に経営する場合は合算した収益がどれくらいになるのかを把握しておかなければなりません。また、収益が少なくても確定申告をしなければならないケースもあることに注意しましょう。
管理業務をすべて外部委託する
管理業務をすべて外部委託するという点も、公務員が許可不要でアパート経営ができる条件です。公務員がみずから賃貸管理業務を行うと事業性があると判断されやすく、副業扱いとなる可能性が高まります。入居者募集や家賃回収、クレーム対応、清掃、修繕手配などの業務を管理会社に委託することで、副業と判断されにくくなるだけでなく、手間を減らすことも可能です。
ただし、委託契約の内容によって判断が異なる場合があるため、賃貸管理委託契約の詳細も事前に確認しておく必要があります。契約書には業務範囲を明確に記載し、自分が直接管理業務に関与しないことを証明できるようにしておくことが望ましいといえます。
公務員が条件を超えてアパート経営をする場合は?

5棟10室以上の規模や年間家賃収入500万円以上など、公務員がアパート経営できる条件を超える場合は、所定の手続きが必要になります。許可なく条件を超えたアパート経営を行うと、懲戒処分の対象になることもあるため、事前に申請を行わなければなりません。
また、公務員から転職・退職した場合でも、在職中からアパート経営を行っていた場合は申請を求められることがあります。許可を得るためには、本人が業務に関与しないことや、安定的な収益が期待できること、職務に支障が出ないことなどを満たしているかがポイントです。
さらに、将来的な収益計画や管理体制を明確にした書類の提出が求められるケースが多く、事業計画書や管理委託契約書などを準備しておくとスムーズです。申請から許可までには一定の時間がかかるため、余裕を持って手続きを進めることをおすすめします。
公務員がアパート経営を始めるためのステップ
公務員がアパート経営を始める際は、適切な手順を踏むことが重要です。ここでは、アパート経営を始めるための具体的なステップについて解説します。
1. 事前準備と情報収集
公務員がアパート経営を始めるにあたっては、まず事前準備と情報収集が大切です。所有している土地や購入予定の土地の活用可能性を調査し、立地条件や周辺の賃貸需要を分析します。建築可能な構造・階数、駐車場の確保なども含めて、事前調査を行います。
次に、複数の建築会社・設計事務所に相談して、土地に適した建築プランや収支シミュレーションを比較検討しましょう。その際、建ぺい率や容積率なども確認し、実現可能な計画を立てることが大切です。複数社から見積もりを取ることで、適正な建築費用や収益性を判断しやすくなります。
2. 申請手続きの実施と許可取得
事前準備の後は、各種手続きや申請を行います。建築前の段階で申請しておくのが望ましいため、計画が固まった時点で早めに動き出すことが重要です。申請内容は事前に勤務先へ確認しておく必要があり、事業概要や管理委託計画について書類を求められるケースもあります。
これらの書類を準備して勤務先に提出しますが、承認までに時間がかかることもあるため、余裕を持って手続きを進めましょう。申請が不要な規模であっても、念のため勤務先に確認しておくと安心です。
3. 建築・契約・運営の準備と開始
勤務先から許可を得られたら、建築会社と正式に契約し、着工に進みます。建築中も定期的に現場を確認し、計画どおりに進んでいるかをチェックすることが大切です。完成後は管理会社と契約を結び、運営体制を整えましょう。管理会社に入居者募集や家賃回収、クレーム対応などを一任することで、職務に支障をきたさずに経営できます。
アパート経営開始後は、定期的に収支や稼働状況を確認し、必要に応じて修繕や条件見直しなどを適宜実施します。長期的に安定した経営を続けるためには、管理会社との良好な関係を維持することも重要なポイントです。
公務員がアパート経営を行うメリット

では、公務員がアパート経営を行うことでどのようなメリットがあるのでしょうか。続いては、公務員がアパート経営を行う主なメリットについて見ていきましょう。
安定収入で融資審査が通りやすい
公務員がアパート経営を行うメリットとして、安定収入で融資審査が通りやすいという点が挙げられます。公務員は安定した給与と高い職業的信用により、金融機関のローン審査において有利に働きます。民間企業の会社員と比較しても、公務員は雇用が安定しているため、返済能力が高いと評価されやすいのです。
その結果、低金利での融資を受けやすく、資金調達の負担を軽減できます。また、長期ローンも組みやすく、少ない自己資金でアパート経営を始められるケースも多いといえるでしょう。
不労所得としての安定収入を確保できる
不労所得として給与以外の収入源ができることで、生活の安定や老後資金の準備に役立つという点もメリットといえます。アパート経営は、管理会社に業務を委託することで、自分が直接働かなくても家賃収入を得られる仕組みです。景気変動の影響を受けにくい住居系賃貸のため、長期的に安定した収入が期待できます。
また、年金以外の安定収入を確保できるため、将来的な生活の安定にもつながります。退職後も継続して家賃収入を得ることで、生活の質を維持しやすくなり、老後の不安を軽減できるでしょう。
相続税対策や節税効果も期待できる
相続税対策や節税効果を期待できる点も、アパート経営を行うメリットのひとつです。不動産は現金よりも相続税評価額が低いため、アパート経営を行うことで節税効果が期待できます。
また、相続や生前贈与で取得した物件の経営は、所属機関からも許可を得られやすい傾向にあります。さらに、減価償却などの税制優遇もあり、確定申告を行えば税負担を軽減することが可能です。建物部分の減価償却費を経費として計上すれば、所得税や住民税の負担軽減につながります。
公務員のアパート経営における注意点
アパート経営にはメリットがある一方で、注意しなければならない点もあります。最後に、公務員がアパート経営を行う際の主な注意点について解説します。
法令違反による懲戒処分のリスク
公務員が許可なしでアパート経営できる条件を満たしていなかったり、申請が必要なのに申請しなかったりした場合は、減給や懲戒免職などの処分を受ける可能性があります。法令に違反した場合、経営規模や収入額にかかわらず、厳しい処分が下されることがあるため注意が必要です。
勤務先に知られることはないと思っても、住民税は給与から天引きされるため、副収入があると住民税額が増えて、経理部門が気づくケースもあります。また、同僚や知人との会話から情報が漏れることもあるでしょう。
リスクを回避するためには、事前の申告と適切な申請が大切です。少しでも不安がある場合は、勤務先に相談してから始めることをおすすめします。
空室対策
アパート経営の際に注意しておきたいのは、空室リスクへの対策です。アパート経営は必ず成功するわけではなく、空室リスクや修繕費の増加などの課題があります。立地条件や周辺環境の変化により、入居者が集まらないケースもあるでしょう。
空室が続くと家賃収入が減少し、ローン返済に支障をきたす可能性もあるため、事前の需要調査が重要です。また、建物の老朽化に伴う大規模修繕や設備更新には、まとまった費用がかかります。入居率を高めるための工夫や、家賃設定の見直し、リフォームの実施など、長期的な視点で戦略的に経営を行うことが大切です。
税務手続きと確定申告の義務
アパート経営には、税務手続きと確定申告の義務があることにも注意が必要です。アパート経営で得た不動産所得は確定申告が必要で、申告漏れは罰則の対象となります。
公務員であっても、副収入がある場合は自分で確定申告を行わなければなりません。年間の家賃収入から必要経費を差し引いた金額が不動産所得となり、給与所得と合算して税額が計算されます。毎月の帳簿付けや領収書の保管、期限内の申告が求められるため、日頃から収支管理を行うことが重要です。
特に初めて確定申告を行う場合は、税理士への相談や依頼も検討し、正確な申告を心がけるようにしましょう。
アパート経営は公務員でも可能。ルールを守って始めよう
公務員でも、5棟10室未満の規模、年間家賃収入500万円未満、管理業務の外部委託などの条件を守れば、アパート経営が可能です。条件を超える場合は、事前に所属機関に申請し、許可を得ることで経営できます。アパート経営は、不労所得として将来の安定収入を築けるメリットがある一方、法令違反による懲戒処分のリスクや、空室対策、税務手続きなど、注意すべき点も理解しておく必要があります。
アパート経営を検討する際は、専門家のサポートを受けることが成功への近道です。セレ コーポレーションは、アパート建築・経営の専門会社として、土地活用や建て替え相談をはじめ、資金計画や設計までトータルに支援しています。公務員の方でも安心して相談できる体制が整っているため、アパート経営に興味がある方は、ぜひセレ コーポレーションにお問い合わせください。
いまさら聞けない!
アパート経営の疑問を解消
自己資金、利益、空室対策…
アパート経営によくある不安と解決策をまとめました。
今なら無料で、メールにてお届けします。

< この記事の監修者 >

斎藤 岳志
FPオフィス ケセラセラ横浜代表
1977年横浜市生まれ。2001年上智大学文学部哲学科卒。
百貨店、税理士事務所、経営コンサルタント会社勤務などを経て、2013年にケセラセラ横浜を開設。
信用取引や商品先物取引、FXなど様々な投資を経験し、その中で自身に一番合うと感じた大家業を2007年にスタート。不動産投資に関するアドバイスを中心としたファイナンシャルプランナーとして活動中。
金融資産は、イデコやNISAを活用しながら、実物資産は、中古ワンルームを活用しながら、
身銭を切って、自らも資産形成中のプレイヤーでもある。
アパート経営について関連記事を探す
■アパート経営の基礎知識
サラリーマンがアパート経営するには?節税効果や始め方を解説
アパート経営の家賃収入の内訳は?収支シミュレーションを紹介
【アパート経営でかかる税金の基本】シミュレーションや節税のコツ
アパート経営の相談はどこにする?相談先の選び方と準備を解説
【新築アパート投資の基本】仕組みやメリット・デメリットを解説
アパート(賃貸)経営とは?メリットやリスク、始める流れを解説
アパート(賃貸)経営の初期費用は?維持費用や自己資金の目安を解説
アパート建築の基本的な段取りを解説! 費用や時間はどのくらい必要?
アパートローンが基礎から分かる! 金利や審査基準とは? 住宅ローンとどう違う?
個人と法人の違いとは? 学んで得する賃貸アパート経営の手引き
統計から考える! アパート経営するなら知っておきたい首都圏住宅事情
■アパート経営の失敗・対策ガイド
アパート経営は地獄?失敗する理由と成功させるポイントを解説
アパート経営はやめたほうがいい?するなと言われる理由や対策を解説
アパート(賃貸)経営は儲からない?理由や成功させるポイントを解説
押さえておきたいアパート経営年間スケジュール。日頃から対策すべきこととは?
■アパート経営の収益・収支ガイド
アパート経営の利回りの最低ラインと理想は?計算方法や相場を解説
アパート経営は何年で黒字化する?期間の目安や成功のコツを解説
不動産投資で理想の利回りは何%? 基本の計算方法や相場など基礎知識を解説
賃貸併用住宅とは?どんな人に向いている?特徴とメリット・デメリットを解説